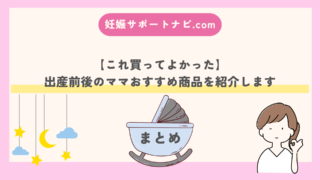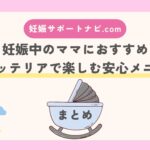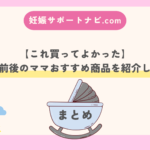出生前診断は、妊娠中に血液検査や超音波検査を行い、お腹の中の赤ちゃんについて調べる検査です。出生前診断にはいろいろな種類がありますが、「どの検査を受ければよいのか」「そもそも受けるべきなのか」と迷ってしまう妊婦さんは少なくありません。
この記事では、出生前診断の基本から各検査の特徴まで、妊婦さんにとって本当に必要な情報をわかりやすくお伝えします。
そもそも出生前診断って何?
出生前診断とは、赤ちゃんに生まれつきの病気がないかを妊娠中に調べる検査です。「赤ちゃんの状態を事前に知り、最適な分娩や出産後の治療、療育環境を準備すること」が主な目的になります。
非確定検査は病気の可能性を調べるためのスクリーニング(ふるい分け)検査で体への負担が少なく、確定検査は診断を確定するための検査です。
出生前診断の種類と特徴比較
出生前診断には、主に以下の6つの種類があります。
| 種類 | 検査名 | 検査時期 | ダウン症検出率 | 費用 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|
| 非確定検査 | 超音波(エコー)検査 | 妊娠初期~ | – | 健診費用内 | なし |
| 母体血清マーカー | 15~17週頃 | 約80% | 2万~3万円程度 | なし | |
| コンバインド検査 | 11~13週頃 | 約85% | 5,000~5万円程度 | なし | |
| NIPT | 10週~18週頃 | 約99% | 10万弱~20万円程度 | なし | |
| 確定検査 | 羊水検査 | 15〜18週頃 | ほぼ100% | 10万~20万円程度 | 流産約0.1~0.3% |
| 絨毛検査 | 11~14週頃 | ほぼ100% | 10万~20万円程度 | 流産約0.3~1% |
結論から言うと、出生前診断の中でNIPT(新型出生前診断)が最も精度が高く、安全性にも優れています。
以下では、各検査について詳しくみていきましょう。
非確定検査の特徴
非確定検査は、超音波や妊婦さんからの採血のみで、赤ちゃんの病気の可能性を調べる検査です。
体への負担が少なく死産や流産のリスクも極めて低いですが、染色体疾患が疑われる検査結果が出た場合は、診断を確定するための確定検査が必要となります。
ここでは、非確定検査の詳細を説明します。
超音波(エコー)検査
妊婦健診で行われる、妊婦さんにとって最も身近な検査です。費用は健診に含まれており、追加負担はありません。
胎児の形態異常(心臓の構造、脳の発育、手足の形など)を観察できる点が特徴で、NT(後頸部浮腫)の測定などから染色体異常を示す手がかりを発見できます。
あくまでスクリーニング(ふるい分け)であり、超音波検査単独での染色体異常の確定診断はできません。
母体血清マーカー検査(クアトロテスト)
妊婦さんの血液中の成分(AFP、hCG、uE3、Inhibin A)を測定し、21トリソミー(ダウン症)・18トリソミー・神経管閉鎖不全症の確率を調べる検査です。
費用は比較的手頃で、検査精度は80%前後というデータもあります。ただし、これは公的に統一された数値ではなく、あくまで目安です。
ただし、偽陽性がでる場合もあるので、陽性でも実際には異常がないケースも少なくありません。
出典:出生前検査認証制度等運用委員会|母体血清マーカー検査とは
コンバインド検査
血液検査と超音波検査(NT測定など)を組み合わせた検査方法です。妊娠初期に実施できるため、早い時期に赤ちゃんの状態を知りたい方に適しています。
2つの検査を組み合わせることで、母体血清マーカー検査単独よりもやや高い精度(約82~87%)が期待できます。
※出典:出生前検査認証制度等運用委員会|超音波マーカーの検査・コンバインド検査
NIPT(新型出生前診断)
母体の血液中に含まれる胎児由来のDNA断片を解析して、21トリソミー(ダウン症)、18トリソミー、13トリソミーの可能性を調べる検査です。非常に高精度な点が最大の特徴で、陰性的中率は99.99%以上となります。
日本のNIPTコンソーシアムの10万件以上のデータによると、陽性が出る確率は全体で約1.8%、ダウン症の陽性的中率は97.3%(陽性でも約2.7%は偽陽性)です。
出典:出生前検査認証制度等運用委員会|NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)
出生前検査認証制度等運用委員会|NIPTを受けた10万人の妊婦さんの追跡調査
確定検査
確定検査は、染色体疾患の特定・確定をするために行う検査です。安全性の高い検査ですが、妊婦さんのお腹に針を刺して調べる必要があるので、流産の可能性を否定できません。
次は、確定検査の詳細をみていきましょう。
羊水検査
超音波で赤ちゃんの位置を確認しながら妊婦さんのお腹に細い針を刺し、羊水を20ml程度採取する検査です。羊水中には赤ちゃんから剥がれ落ちた細胞が含まれているので、染色体異常をほぼ100%の精度で診断できます。
従来は流産リスクが0.3%程度とされていましたが、最近の大規模研究ではさらに低いことが報告されました。検査後は、約2~3週間で結果が出ます。
※出典:出生前検査認証制度等運用委員会|羊水検査
Salomon LJ, et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;54(4):442-451
絨毛検査
羊水検査と同様に妊婦さんのお腹に針を刺すか、子宮頸部にカテーテルを挿入して絨毛(胎盤の組織)を採取する検査です。料金は10~20万円程度で、2~3週間で結果を知ることができます。
羊水検査より早い時期に検査ができるため、非確定検査で気になる所見が認められたときなど、早期に診断を確定したいケースにおすすめです。
従来は流産リスクが約1%とされていましたが、経腹法(お腹に針を刺す方法)の経験豊富な施設では、羊水検査と同程度という報告もあります。ただし、胎盤のみに染色体異常があり、赤ちゃんは正常というケースが1%程度存在するので、結果が陽性の場合は羊水検査で再確認が必要になることがあります。
※出典:出生前検査認証制度等運用委員会|絨毛検査
兵庫医科大学病院|絨毛検査とは
NIPT検査が選ばれる理由とメリット・デメリット
ここまでさまざまな出生前診断をご紹介してきましたが、そのなかでも注目されているのが、NIPT(新型出生前診断)です。
NIPTが多くの妊婦さんに選ばれているのは、「高い精度」「安全性」「早期検査」という3つの大きなメリットがあるからです。
ここでは、NIPTのメリットとデメリットについて紹介します。
NIPTのメリット・デメリット
| NIPTのメリット | NIPTのデメリット |
|---|---|
| ✓ ダウン症の陽性的中率97.3%の高精度 | × 費用が高い(10万弱~20万円程度) |
| ✓検査による流産リスクゼロ | × 非確定検査(陽性でも確定ではない) |
| ✓ 妊娠10週頃から検査可能 | × すべての病気がわかるわけではない |
| ✓ 陰性なら99.9%以上の確率で安心 | × 結果によっては精神的負担が大きい |
NIPTの最大の強みは「高精度と安全性の両立」です。従来の母体血清マーカー検査と比較しても圧倒的に高い精度でありながら、検査による流産リスクがありません。
ただし、検査には限界があることも理解しておきましょう。
NIPTは主に3つのトリソミーのみを対象としており、先天性疾患全体の約17~18%程度しかカバーしていません。検査結果が陰性でも他の染色体異常や形態異常は検出できないうえ、陽性の場合は確定検査が必要となります。
認証施設vs非認証施設
NIPTを受けると決めたあとは、「どこで検査を受けるか」を考えていきましょう。
日本では2022年以降、「出生前検査認証制度等運営委員会」による認証制度が運用されており、検査は「認証施設」もしくは「非認証施設」で受けることになります。
| 項目 | 認証施設 | 非認証施設 |
|---|---|---|
| 遺伝カウンセリング | 必須 | 施設により異なる |
| 来院 | 夫婦同伴 | 一人でもOK |
| 予約 | 取りにくい | 取りやすい |
| 費用 | やや高め | 比較的安い |
| 陽性時のサポート | 確定検査への連携体制が整備 | 施設により異なる |
| 検査項目 | 主に3トリソミー(21,18,13番) | 施設により拡張検査あり |
※施設によって異なるので、詳細は希望施設へ事前にお問い合わせください。
認証施設は遺伝カウンセリングが必須で、検査前に検査の意義や限界、結果が出た場合の選択肢について、遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーから丁寧にしてもらえます。また、確定検査(羊水検査)への連携体制が整備されているので、検査結果が出た後のフォロー体制も充実しています。
非認証施設の最大のメリットは、予約の柔軟性と利便性です。一人での来院が可能で、土日も対応している施設が多く、仕事や育児で忙しい方でも受けやすい環境が整っています。
費用を抑えて便利にNIPTを受ける方法
仕事や育児で忙しく、費用も抑えたいという方には、Jラボのような非認証施設が現実的な選択肢となります。
ここでは、非認証施設の一例として全国展開しているJラボについてご紹介します。
Jラボの特徴
Jラボは全国に提携クリニックを持つ非認証施設で、最大の特徴は「全国どこでも」「一人でも」「土日でも」検査を受けられる利便性の高さです。
| Jラボの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国の提携クリニックで検査可能 |
| 費用 | 基本検査9万3,500円(税込)~ (診察料・カウンセリング料不要) |
| 利便性 | 一人での来院OK、土日も対応 |
| 保証 | 陽性時の羊水検査費用全額保証 |
診察料やカウンセリング料が不要なため、基本的なNIPT検査が93,500円(税込)から受けられます。認証施設と比較すると、5~10万円程度安くなることも珍しくありません。
利用方法や料金の詳細については、公式サイトでご確認ください。
検査前の準備
NIPT検査を受ける前には、ご夫婦でしっかりと話し合うことが何より大切です。 「なぜ検査を受けたいのか」「もし陽性だったらどうするか」について事前に考えておくことで、いざというときに冷静に判断できます。
もちろん、検査を受けないという選択も尊重されます。正しい情報を得たうえで、ご自身とご家族にとって最適な選択をしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. NIPTはいつから受けられますか?
A. 妊娠10週0日から受けることができます。
陽性の場合に確定検査(羊水検査など)を受けるタイミングを考慮して、多くの施設では妊娠15週頃までに受けることを推奨しています。
Q. NIPTで陽性が出る確率はどのくらいですか?
A. 年齢によって異なりますが、全体では約1.8%程度です。
高齢での妊娠を理由に検査を受けた場合は約1.5%、母体血清マーカー検査で陽性だった方が受けた場合は約4.1%という日本のデータがあります。
※出典:出生前検査認証制度等運用委員会|NIPTを受けた10万人の妊婦さんの追跡調査
Q. 双子の場合でもNIPTは受けられますか?
A. はい、双子でも検査は可能です。
ただし、単胎妊娠と比べて精度がやや下がる場合があり、判定保留になる可能性も高くなります。そのため多胎妊娠の際は認証施設での検査が推奨されます。
Q. NIPTで異常なしと出れば、赤ちゃんは完全に健康ですか?
A. いいえ、NIPTは特定の染色体異常のみを調べる検査です。「調べた範囲では異常なし」という意味になります。
Q. 保険は使えますか?
A. 残念ながら、NIPTは保険適用外のため全額自己負担となります。また、基本的に医療費控除の対象にもなりません。
まとめ
出生前診断にはさまざまな選択肢がありますが、現在注目を集めているのがNIPT(新型出生前診断)です。約99%という高い精度と検査による流産リスクゼロの安全性を理由に、多くの妊婦さんに選ばれています。
どちらを選ぶにしても、ご夫婦でしっかりと話し合い、納得のいく決断をすることが大切です。
妊娠中の不安は自然なものです。正しい情報を得て、ご自身とご家族にとって最適な選択をしていただければと思います。