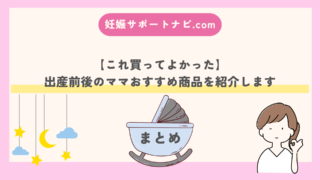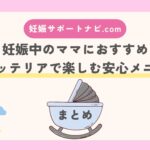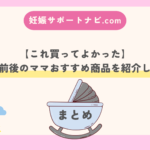のどぐろって高級魚で、スーパーではなかなか見かけないけれど、実は赤ちゃんの成長に嬉しい栄養素がぎゅっと詰まった優秀な食材なんです。でも、いつから食べさせていいのか、どうやって調理すればいいのか、特に干物は離乳食に使えるのか迷ってしまいますよね。
実は、のどぐろは白身魚なのに脂肪分が多いという特徴があるため、離乳食での取り扱いには少しコツが必要。でも心配はいりません。適切な方法さえ知っていれば、赤ちゃんにとって素晴らしい栄養源になってくれるはずです。
のどぐろは離乳食でいつから食べられる?
のどぐろを離乳食に取り入れるタイミングから、注意すべきポイントまで、段階的に見ていきましょう。赤ちゃんの成長に合わせた適切な進め方を知っておけば、安心してのどぐろデビューができますよ。
のどぐろは中期からスタート
のどぐろは確かに白身魚に分類されるものの、一般的な白身魚と比べて脂肪分が多いのが特徴です。そのため、離乳食初期ではなく中期(生後7〜8ヶ月頃)からのスタートが安心。鯛やヒラメのような淡白な白身魚に慣れてから挑戦するのがおすすめです。
鯛やヒラメ、カレイなど他の白身魚であれば離乳食初期から与えることができますが、のどぐろの場合は赤ちゃんの消化器官がもう少し発達してからの方が負担をかけにくいんです。脂肪分が多いと消化不良を起こしやすくなるため、最初は小さじ1杯程度の少量から始めて、赤ちゃんの様子を見ながら量を調整していきましょう。
離乳食初期に与える白身魚は、消化がよく淡白な味のものが基本。のどぐろは美味しいけれど、濃厚な旨味があるので、赤ちゃんの味覚が発達してからの方がその美味しさを楽しめるかもしれませんね。また、脂肪分が多い魚は満腹感を得やすいため、他の食材とのバランスも考慮する必要があります。
干物は基本的に離乳食には不向き
スーパーや魚屋さんでよく見かけるのどぐろの干物ですが、離乳食には基本的に向いていません。干物は保存のために大量の塩が使われており、赤ちゃんの未発達な腎臓には負担が大きすぎるからです。
また、水分が抜けて身が硬くなっているため、赤ちゃんには食べにくく、のどに詰まらせてしまう危険性も。どうしても干物を使いたい場合は、焼いた後に熱湯で10分以上塩抜きをして、身を細かくほぐし、とろみをつけるなどの工夫が必須です。
干物を与えるなら3歳前後からが安心とされており、離乳食期は新鮮な生ののどぐろを選ぶのが無難でしょう。
アレルギーや消化不良に注意しながら進める
のどぐろは魚介類アレルギーの原因となることがあるため、初めて与える時は平日の日中がおすすめ。万が一アレルギー反応が出た場合に、すぐに小児科を受診できるよう配慮しておくと安心です。土日や夜間では、かかりつけの小児科が開いていないことが多いので、平日の午前中に試すのがベストタイミングといえるでしょう。
また、赤ちゃんの消化器官はまだ未熟なため、食べ過ぎると下痢や嘔吐などの消化不良を起こすことも。最初は耳かき1杯程度から始めて、様子を見ながら少しずつ量を増やしていきましょう。便の状態や機嫌、食欲などをよく観察して、変化があればいったん中止することも大切です。
他の新しい食材を同時に与えるのは避けて、1種類ずつ進めていくのが基本です。もし何かトラブルがあった時に、原因を特定しやすくなりますからね。のどぐろを与える前に、他の白身魚でアレルギー反応が出ていないか確認しておくと、より安心して進められます。
アレルギー症状としては、湿疹、かゆみ、嘔吐、下痢などが一般的ですが、重篤な場合は呼吸困難や意識レベルの低下なども起こりえます。食後2時間程度は特に注意深く観察し、気になる症状があれば迷わず医療機関を受診しましょう。
のどぐろの栄養価と赤ちゃんへのメリット
のどぐろが「高級魚」と呼ばれるのは、その美味しさだけでなく、栄養価の高さにも理由があります。赤ちゃんの成長に必要な栄養素がバランスよく含まれているので、上手に取り入れれば強い味方になってくれるでしょう。
ビタミン・ミネラルが豊富
のどぐろにはビタミンB12、ビタミンD、ビタミンEをはじめとする各種ビタミンが豊富に含まれています。特にビタミンB12は野菜からは摂りにくい栄養素なので、魚類からの補給が重要なんです。ビタミンB12は神経系の発達や造血作用に欠かせない栄養素で、不足すると貧血や神経障害を起こす可能性があります。
ビタミンDは骨や歯の形成に必要で、カルシウムの吸収を促進する働きがあります。日光を浴びることでも体内で合成されますが、赤ちゃんは外出の機会が限られているため、食事からの摂取も大切です。
ミネラル面では、マグネシウム、リン、銅、カリウム、カルシウムなどが豊富。マグネシウムは骨や歯の形成だけでなく、筋肉の収縮や神経伝達にも関わる重要なミネラルです。リンはカルシウムと結合して骨や歯を作る材料となり、銅は鉄の吸収を助けて貧血予防にも役立ちます。
カリウムは体内の水分バランスを調整し、ナトリウム(塩分)の排出を促進する働きがあるため、将来の高血圧予防にもつながると考えられています。
必須脂肪酸DHA・EPAが脳や体の発達に役立つ
のどぐろの大きな魅力は、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などの必須脂肪酸が豊富なこと。DHAは脳細胞の活性化に役立ち、特に記憶や学習に関わる海馬という部分の発達に重要な役割を果たします。EPAは血液をサラサラにして血流を改善し、炎症を抑える働きも期待できます。
必須脂肪酸は体内で合成することができないため、食事からの摂取が欠かせません。特に脳の発達が著しい乳幼児期には、質の良い脂肪酸をしっかり摂取させてあげたいですね。妊娠中や授乳中のお母さんが魚を積極的に食べることで、赤ちゃんにも良い栄養が届きます。
DHAは網膜の構成成分でもあり、視力の発達にも欠かせません。また、免疫系の調整にも関わっているため、アレルギー症状の軽減にも役立つ可能性があります。EPAには血管を柔らかく保つ働きがあり、将来の生活習慣病予防にもつながると考えられています。
のどぐろ100gあたりのDHA含有量は約2000mg、EPA含有量は約1500mgと、青魚に匹敵する高い数値を示しています。
良質なたんぱく質で赤ちゃんの成長を支える
たんぱく質は赤ちゃんの筋肉や内臓、皮膚、髪の毛など、体を作るために欠かせない栄養素。のどぐろには消化吸収しやすい良質なたんぱく質が豊富に含まれているため、成長期の赤ちゃんにとって理想的な食材といえるでしょう。
お粥や軟飯に混ぜたり、茹でた野菜と一緒に煮込んだりして、主菜として活用してみてください。植物性たんぱく質の豆腐や豆類と組み合わせることで、アミノ酸バランスもさらに良くなりますよ。
赤ちゃん向けのどぐろ調理のポイント
栄養豊富なのどぐろも、調理方法を間違えると赤ちゃんには食べにくくなってしまいます。安全で美味しい離乳食にするためのコツを押さえておきましょう。冷凍保存の方法も含めて、日々の離乳食作りが楽になるヒントをお伝えします。
しっかりと火を通す
のどぐろを離乳食に使う時は、塩や調味料は一切使わず、弱火から中火でじっくりと火を通すのが基本です。焦がさないよう注意しながら、中まで完全に火が通るまでしっかりと加熱しましょう。
焼き上がったら、皮と骨を丁寧に取り除きます。特に小骨は見落としがちなので、身をほぐしながら指先で確認することが大切。ほぐした身はそのままでも食べられますが、お粥や軟飯に混ぜたり、茹でた野菜と和えたりすると食べやすくなります。
パサつきが気になる場合は、だし汁や野菜スープでのばしたり、片栗粉でとろみをつけたりすると食べやすくなります。
干物や加工品は塩抜きを忘れずに
どうしても干物を使いたい場合は、焼いてから熱湯に10分以上浸して塩抜きを行います。焼く前に塩抜きをする方法もありますが、焼いた後の方が身がほぐれやすく、骨も取り除きやすくなるのでおすすめです。
塩抜きが終わったら、骨や皮を丁寧に取り除き、すり鉢でなめらかになるまですりつぶします。手間はかかりますが、赤ちゃんが安全に食べるための大切な工程です。
のどぐろのすり身製品を使う場合も、塩分が多く含まれているため同様に塩抜きしてから利用しましょう。
冷凍ストックはパサつかないようにひと工夫!
のどぐろは火を通して身をほぐしてから冷凍保存しておくと、離乳食作りがぐっと楽になります。製氷皿に小分けして冷凍すれば、必要な分だけ解凍して使えて便利ですよ。
ただし、他の白身魚と同様に、加熱しすぎるとパサつきやすいのが難点。冷凍保存する際は、だし汁や野菜スープと一緒に冷凍すると、解凍した時のパサつきを軽減できます。
解凍後は、お粥やスープに加えたり、野菜と一緒に煮込んでつみれ風にしたりするのがおすすめ。水分やとろみがあると、赤ちゃんも食べやすくなります。
まとめ
のどぐろは栄養価が高く、赤ちゃんの成長に嬉しい食材ですが、脂肪分が多いため離乳食中期からのスタートが安心です。干物は塩分が多すぎるため、離乳食期は避けて新鮮な生のものを選びましょう。
調理する際は塩や調味料を使わず、しっかりと火を通して骨を丁寧に取り除くことが大切。初めて与える時は平日の日中にして、アレルギー反応に注意しながら少量ずつ進めていきましょう。
DHA・EPAなどの必須脂肪酸やビタミン・ミネラルが豊富なのどぐろは、上手に取り入れれば赤ちゃんの健やかな成長をサポートしてくれます。冷凍保存を活用しながら、無理なく離乳食に取り入れてみてくださいね。
妊娠サポートナビ.comには離乳食に関する記事もたくさんあります。ぜひ他の記事も読んでみてくださいね。
\こちらもよく読まれています/