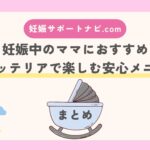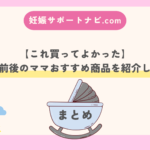果物の女王とも呼ばれる洋ナシは、柔らかく甘い果肉と芳醇な香りが特徴の人気フルーツ。「赤ちゃんと一緒に食べたいけれど、いつから与えていいの?」「アレルギーが心配…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、洋ナシは栄養たっぷりで消化も良く、離乳食初期から取り入れられる優秀な食材なんです。今回は、赤ちゃんに洋ナシを与える際の時期や注意点、簡単おいしいレシピまで詳しくご紹介します。
洋ナシはいつから食べられる?
洋ナシはその柔らかい食感と自然な甘みから、赤ちゃんの離乳食に最適な果物の一つです。月齢に合わせた与え方のポイントを見ていきましょう。
離乳食初期からOK!
洋ナシは離乳食初期(生後5〜6ヶ月頃)から安心して取り入れられる果物です。この時期の赤ちゃんは舌で潰せるような柔らかさの食べ物しか受け付けないため、最初は皮をむいて芯を取り除き、すりおろした状態にして電子レンジで軽く加熱し、お湯で薄めて与えましょう。
洋ナシに含まれる自然の甘みは赤ちゃんの味覚を刺激し、食べる楽しさを覚えるきっかけになります。また、加熱することでアレルギー物質が分解されやすくなり、初めて食べるときの安全性が高まります。
月齢別の与え方の目安
赤ちゃんの成長に合わせて、洋ナシの形状や量を調整していきましょう。
離乳食初期(5〜6ヶ月頃)ごろは皮をむいて芯を取り除き、すりおろすか裏ごしして滑らかなペースト状にします。初めは小さじ1杯からスタートし、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に量を増やしていきましょう。
離乳食中期(7〜8ヶ月頃)ごろの赤ちゃんに与える場合は舌でつぶせる固さになるよう、皮をむいた洋ナシを2〜3mm角に刻んで与えます。この頃になると徐々に食べる量も増えてくるので、一度に小さじ2〜3杯程度から始めてみてください。
離乳食後期(9〜11ヶ月頃)は歯茎でつぶせる固さを目安に、約5mm角に切った洋ナシを与えます。この時期は手づかみ食べの練習にもぴったりの食材ですので、小さめのスティック状に切って渡してみるのもよいでしょう。
離乳食完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)で喉に詰まらせる心配が少なくなれば、前歯でかじって食べられるように一口大に切った洋ナシを与えることができます。
生で与えられるのはいつから?
生の洋ナシを与えられるようになるのは、離乳食後期(9〜11ヶ月頃)からが目安です。ただし、与える際には必ず完熟した柔らかい洋ナシを選びましょう。洋ナシは追熟するフルーツなので、お尻の部分を軽く押して弾力があり少し柔らかく感じるようになったら食べ頃です。
生の洋ナシを与える場合も、皮と芯を必ず取り除き、赤ちゃんが食べやすい大きさに切ることを忘れないでください。最初は小さじ1杯程度から様子を見て、消化状態や異常がないことを確認してから量を増やしていきましょう。
洋ナシを与える際の注意点
赤ちゃんに洋ナシを与える際に知っておきたい注意点について詳しく見ていきましょう。
種と芯を必ず取り除く
洋ナシを赤ちゃんに与える際は、必ず種と芯を取り除くことが重要です。特に芯の部分は固く、赤ちゃんが喉につまらせる危険性があります。また、洋ナシの皮は硬いので、離乳食初期から中期にかけては必ず皮をむいて与えましょう。
最も美味しい部分はお尻の方(枝と反対側、下側)とされています。よく熟れた洋ナシを選び、丁寧に下処理をすることで、安全においしく食べられます。
アレルギー反応に気をつける
洋ナシはバラ科の果物で、食物アレルギーを引き起こす可能性があります。特に同じバラ科の和梨、リンゴ、桃、いちご、さくらんぼ、びわなどにアレルギーがある場合は注意が必要です。
初めて洋ナシを与える時は、次のポイントに気をつけましょう。
1. 小さじ1杯など少量から始める
2. 他の新しい食材と同時に与えない
3. 朝や昼など、万が一の場合に病院を受診できる時間帯に与える
4. 数日間様子を見て、問題がなければ徐々に量を増やす
アレルギー反応のサインとしては、発疹、かゆみ、嘔吐、下痢、咳、ぜいぜいした呼吸などがあります。これらの症状が見られたら、すぐに医師に相談しましょう。
食べ過ぎによる下痢に注意する
洋ナシには食物繊維が豊富に含まれており、一度に大量に食べると消化不良を起こして下痢になる可能性があります。特に離乳食を始めたばかりの赤ちゃんは消化機能が未熟なので、少量から始めて徐々に体を慣らしていくことが大切です。
また、洋ナシはカリウムも多く含まれているため、腎機能が未発達な赤ちゃんに大量に与えるのは避けましょう。適量を守り、バランスの良い離乳食を心がけることが大切です。
洋ナシを使った離乳食レシピ
洋ナシを使った簡単でおいしい離乳食レシピをご紹介します。赤ちゃんの月齢に合わせて試してみてください。
りんごと洋ナシのジュース
甘みの異なる2つの果物を合わせた、さっぱりとした飲みやすいジュースです。食べ物の味に慣れ始めたばかりの赤ちゃんにぴったりで、果物の自然な甘さを楽しめます。
皮を剥いて芯を取り除いたリンゴと洋なしを適量用意してください。ミキサーにかけ、湯冷ましで赤ちゃんが飲みやすい濃さに調整します。必要に応じて加熱すれば、より安心して与えられますよ。
このジュースは離乳食初期から与えることができますが、果汁だけに偏らないよう注意しましょう。最初は小さじ1杯程度から様子を見て、徐々に量を増やしていくのがおすすめです。
洋ナシコンポート
電子レンジで簡単に作れる、洋ナシの甘みを存分に引き出したコンポートです。もぐもぐ期に入った赤ちゃんの舌触り練習にも最適で、果物本来の風味を楽しめます。
皮をむいて小さく切った洋ナシと少量の水だけで作れる、シンプルながら奥深い味わいのレシピです。
作り方は耐熱容器に材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。洋ナシが柔らかくなったら冷まして、赤ちゃんの月齢に合わせて形状を調整します。
加熱することで甘みが増し、素材そのままの美味しさを楽しめるコンポート。離乳食中期以降の赤ちゃんに適していますが、初期の場合はよく潰してから与えましょう。
洋ナシのヨーグルト和え
洋ナシの自然な甘さとヨーグルトのまろやかさが絶妙に調和した一品です。酸味が苦手な赤ちゃんでも食べやすく、腸内環境を整える効果も期待できるおやつとしておすすめです。
材料は洋ナシと無糖のプレーンヨーグルトだけ。シンプルな材料で栄養バランスの良いおやつが作れます。
赤ちゃんの月齢に合わせて洋ナシを適切な大きさに調理し、ヨーグルトと混ぜ合わせるだけの簡単レシピ。時間がないときのおやつにも最適です。
ヨーグルトは離乳食中期(7〜8ヶ月)からこのレシピは離乳食中期以降の赤ちゃん向けです。ヨーグルトを使うことで酸味が緩和され、口当たりが良くなります。初めてヨーグルトを与える場合は、アレルギー反応に注意しましょう。
まとめ
洋ナシは離乳食初期から取り入れられる栄養豊富な果物で、その自然な甘みと柔らかい食感は赤ちゃんの好奇心を刺激し、食べる喜びを感じさせてくれます。与える際は月齢に合わせた形状や量を守り、アレルギーや消化不良に注意しながら徐々に慣らしていくことが大切です。
今回ご紹介した簡単レシピを活用して、赤ちゃんとの食事タイムを楽しく、そして安全に過ごしましょう。
妊娠サポートナビ.comには赤ちゃんにあげる果物に関する記事もたくさんあります。ぜひ他の記事も読んでみてくださいね。
\こちらもよく読まれています/











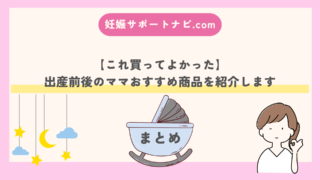
を食べたい|注意点&おすすめレシピをご紹介.png)